大阪・西天満にて2018年にオープンした「十皿」は、季節の食材と粋な器、ワインのマリアージュを味わえるレストラン。オーナーシェフ・真野淳氏の故郷である、淡路島の豊かな風土が生み出す素材を活かした料理がいただけます。今回は「十皿」流の料理の世界についてお伺いしました。
目 次
淡路島の豊かな自然の中で育った青年が『十皿の料理』と出会うまで
―シェフは淡路島出身ということで、島の食材を料理にも使われていますが、料理人を志したきっかけは?
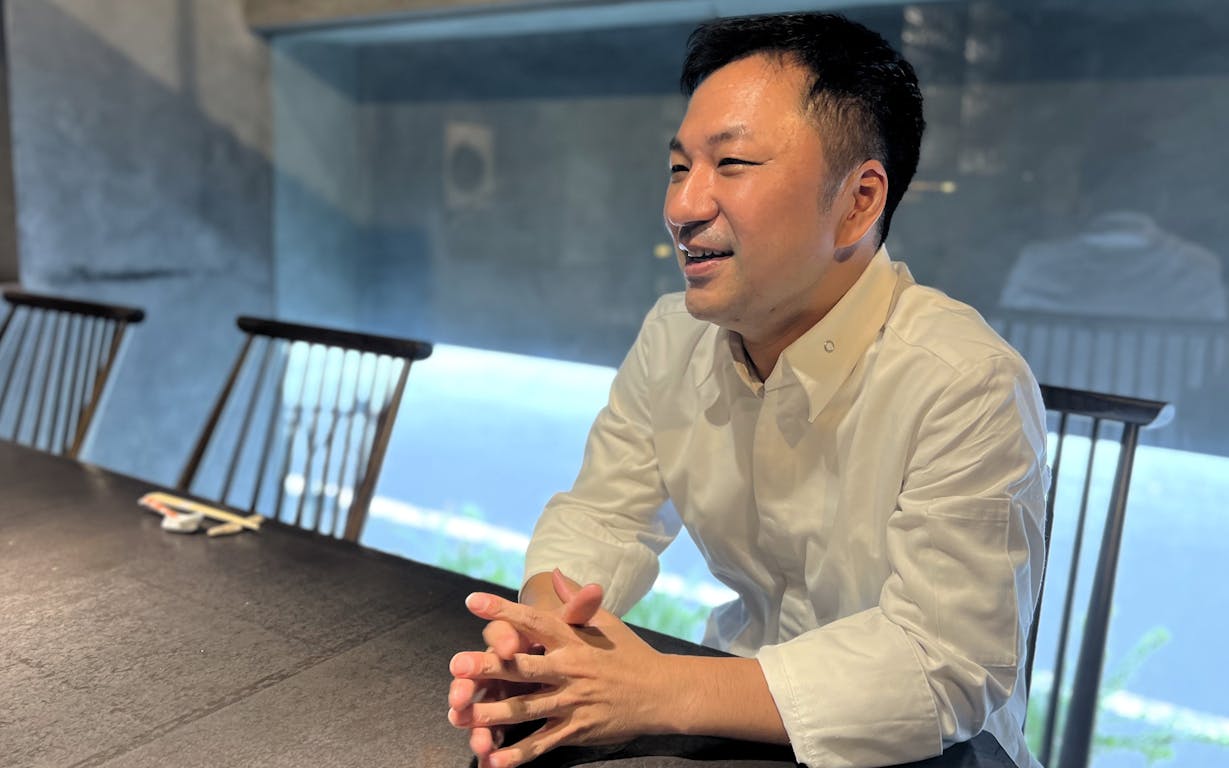
実家が淡路島の南あわじの方で農家と畜産業をしていたので、家の周りは畑や大きな池、牛や鶏などの動物に囲まれた環境で生まれ育ちました。池では魚釣りができて鮒や鰻が釣れるので、魚を捌いたり、畑から玉ねぎやブロッコリー、ピーマンなどの野菜を摘んできたりする生活で、自分で料理を作るのが日常の一部でした。チャーハンを炒めたり、親と一緒に野菜の天ぷらを作ったりするのが好きでした。
学生時代に飲食のアルバイトをする中で、20~21歳の頃にホテルのフレンチレストランで2年間働き、そのまま就職しました。最初は20歳以上年上の方ばかりの職場で、とんでもなく厳しい環境に飛び込んだ状態。めちゃくちゃ怒られましたが、大学に行った上で、やると決めて覚悟を持って料理の世界に入ったので、厳しいから辞めるという選択肢は僕の中にはなかったです。4年間務める中で、ちょっとずつ自分を気にかけてくれる先輩も何人かいらっしゃって、西洋料理の基礎を学ばせてもらいました。
―店名にもなっていますが、その時のホテル時代の先輩から、斉須政雄シェフの著書『十皿の料理』をいただき、感銘を受けられたそうですね。
入社して半年たった頃に先輩から「これを読んで、料理人としての心得を身に着けろ」と言われました。本では、人生を10皿の料理に例えていて、フランスでの修業時代の経験談を読み「多分僕にとって、この本が一生聖書になるんじゃないかな」という気持ちになって、すごく大事にしていました。斉須シェフはすごく謙虚で、料理に対してすごく素直な方だなと。自分の若い頃の甘い感じが、この本によって軌道修正できたように思います。
当時、朝食の仕事を任せてもらうために「オムレツを料理長の前で作れるようになる」という課題がありました。料理長の前では緊張して作れなかったんです。それで、毎朝5時半に出勤してオムレツの練習をさせてもらって、半年ほどかかって漸く作れるようになり、朝食を任せてもらえるようになった。なので、この本を読むといつも、当時の緊張感を思い出し「初心を忘れずに」という気持ちになります。
今の店名を「十皿」と決めたのも、斉須シェフと一緒に働いたことはなくても18年ほどの修業時代を乗り越えられたのは、あの本があったからかなと感じているからです。自分の修業時代の集大成として、今できる精いっぱいの「10皿」で表現しようという気持ちがこもっています。
少し前に「コートドール」に行って、斉須シェフにずっと大事にしていた本を渡したら、直筆のサインをいただきました。厨房はピカピカで、あのお歳になられても料理ができる喜びや思いを変わらず持ってらっしゃるお姿を拝見して「自分ももっとちゃんとしなければ」と改めて感じました。
料理長を任された大阪「スフィーダ」での経験
―その後「スフィーダ」(現在は閉店)では料理長として13年ほどのご経験を積まれましたが、当時はどのようなことを重視して料理を作っていましたか。
「スフィーダ」は「アルチェントロ」グループのオーナーである本窪田雅文氏が作ったお店です。ホテル勤めの頃から色々と食べ歩いている中で、すごく好きなお店でした。働いてみたいと思っていたタイミングが合って、最初は一番下で入ったんですけど、先輩方が辞めていくうちに1年半ほどで料理長になってしまって。本窪田シェフに色々と教わりながらの日々でした。
最初の4年は今まで残してもらっていたレシピで作っていましたが、なかなかうまくいかず「人から教えてもらった料理ではなく自分らしい料理を作ろう」と試作の日々が5~6年続きました。売上も上げたいし、働いているスタッフにも「ここで働いて良かった」と思ってもらいたい。キッチンとサービスが分かれているお店だったので、美味しい料理を作らないとサービスのスタッフに恥をかかせてしまう。美味しい料理さえちゃんと作ってたら、お客様が喜んでくれるからサービスの人も、会話もワインも進めやすい。
当時はスタッフも多かったので、責任を感じていました。プレッシャーの日々でもありましたが、お客様にいいものを届けるために、美味しい料理を作っていくことの大事さを教えられました。
ちょうどその頃、夏休みに淡路島でアートフェスティバルがあって、屋台のような所を2日間借りて、自分で企画を立て、テーマを決めて金額を決め、料理をするということを始めました。「自分にプレッシャーをかけると、何か潜在能力を引き出せるのでは」と思い、春に申込んだんです。
当日まで毎週のように淡路島に見学に行って、漁港や畑を回ったり、色々なご飯屋さんに行くうちに、地元の陶芸家や農家の人と繋がりを持てるようになりました。その方々から食材を分けていただき、こちらが招待するという淡路島での食事会を、お店とは別でやるようになりました。
―今、シェフが淡路島で行っているイベント「島の十皿」の原型のようですね。
10年位前に淡路島で「美観味(さんみ)の会」というのを作りまして、1人1品ずつのコース料理をやってみたり、東日本大震災があった年に、原始的な火だけで料理を作ってみたらどうかというアイデアから、薪でお肉を焼いたり炭火で魚を焼いたりと、火だけの料理をしました。50人ほどのお客様を呼んだらすごく喜んでくれましたね。ガスなどの熱源で作っても美味しくできるんですけど、薪の香りや炎を見ながら食べる楽しさやワクワクする気持ちは、味とはまた別の調味料というか、理屈じゃない美味しさみたいなものを感じられました。クローズキッチンから出てくる料理とは違う反応が見えて「自分のお店ではいつかそういうことをしたいな」とも思いましたね。
食材の旨みをシンプルに伝える「十皿」の料理のストーリー
―独立のきっかけは?
「スフィーダ」は、自分のお店のように思っていて独立したい気持ちがあまりなかったんです。でも、今のお店(「anu」にリニューアル)で料理長を任されている末広シェフは僕の直属の部下で、彼が成長して僕を押し出してくれたからだと思います。独立を考えている頃、新店の串揚げ店の立ち上げをさせていただき、カウンターキッチンとワインの勉強をしました。カウンターで見られながら料理を作ると楽しいし、お客様に近い距離で料理の味と思いを同時に届けられて、それが自分のスタイルに合ってるなと思いました。
―「十皿」は名の通り10皿の構成で表現するというスタイルですが、どういうテーマで料理を作られていますか?
できるだけシンプルに、要素を多くせず、何を食べているのか分かりやすいようにしています。簡単なようでいて、実際はめちゃくちゃ難しくて。皆が知らない調理法や食材を使った方が楽だし、反応も良いかもしれないですが、食べた時に料理の邪魔をしてるということもある。必要なものや食感を組み合わせて、旨みの相乗効果が起こる一品に仕上げることを徹底的にこだわっています。
食材選びに関しては、“今日本で美味しい食材”を中心に決めています。世界中の食材が手に入れば良いのですが、空輸しても時間がかかるし、いい状態のものが必ず入るとも限らないので、できれば9割くらいは近い距離で料理を作りたい。魚介は淡路島を中心に、明石や和歌山の紀伊水道、日本海など、近海のもの。野菜も淡路島を中心に、大阪の伝統野菜など、近い距離のものを使っています。
塩も、淡路島の海水をくみ上げた「自凝雫塩(おのころしずくしお)」を使っています。その海で育ったサワラとかタイを、海からできた塩で合わせるというストーリーのイメージです。
また、神戸ビーフの大半は淡路島で生まれて繁殖農家が育て、大きくなったら兵庫県のブランド牛と言われる各地に売られていくのですが、実家が繁殖農家なので、寝床には藁を敷き、牛の堆肥で玉ねぎやレタスを作るという形で循環しているのを子供の頃から見ていました。
今、うちが定番で出しているのは、藁の香りをつけた神戸ビーフと玉ねぎを組み合わせたものです。一皿の中で、生命の循環をストーリーとして表現する料理が好きですね。
最近、旨味の相乗効果にも着目しています。和食の一番だしは昔からありますが、昆布と鰹節のグルタミン酸・イノシン酸の相乗効果で旨味が何倍にもなるという、理にかなったものです。フランス料理にも、コンソメも野菜のグルタミン酸と鶏のイノシン酸が2時間以上炊くことによって、旨味が発揮されるというものがあります。科学的にちゃんと実証された旨味の組み合わせも、並行して勉強しないといけないなと。
―コースの構成にも仕掛けがあって、お肉の後に土鍋のピラフが登場しますが、どういうアイデアで始まったのですか?
10皿のコースの構成で、どういう流れを作るかを考えた中で生まれました。
最初はあえて胃腸を労わるという形で、温かい料理をお出ししています。和食で言う、一汁二菜のお茶の考え方に則っていて。お茶を楽しむ会でも、茶の成分に渋みがあるため温かいもので胃を労わる、という形です。アルコールも空腹状態で飲むと、胃を痛めるので、最初に優しいお粥や湯豆腐を食べていただいています。
その後にフィンガーフード系。「レストランに来て手づかみでいいの?」と思うかもしれませんが、あえて手づかみで食べたらちょっと緊張がほぐれるため2品目にお出します。続いて、カルパッチョなど。前半でお肉ではないメインの後に、パスタが続きます。後半はスープ仕立てのお魚料理で、次のお肉に繋がるように。
肉料理は旨味が強いため、本来はそこで満腹感があるんです。でも、日本人の食事は最後に締めの食事があり、米は別腹というか。最後に炭水化物的なものを入れたいっていう需要があるんですよね。だけど僕なら、ある程度メインで満足した後に、油を使ったリゾットも乳化させたパスタも食べたくなくて。もし最後に締めるなら「ご飯かな」と思い、実家で取れる米を使ったものを出すことにしました。
ただ、普通の炊き込みご飯ではなく、香味野菜を油でゆっくり炒めて作る「ソフリット」を入れています。本来のピラフは、そのソフリットと米を一緒に炒めて、出汁を入れて炊くんですが、油で炒めたソフリットを入れて米にちょっと油分をまとわすような、ぱらっとしたスタイルにしています。
ご飯を食べたらもうお腹はいっぱいだけど、デザートは別腹でいただける。10皿の中で起承転結の流れを作ると、初めは多いかなと思うんですが、最後まで食べられますね。
締めの食事はオープン初日ぐらいまでどうしようか悩み、最初の頃は、白いご飯とレンコンの鬼おろしにバターを入れるだけのシンプルなものをお出ししていたら「バターライスのようで美味しい」と評判が良くて。このまま土鍋ご飯を続けることにしました。
―「十皿」では、器にもこだわっているそうですね。
器との出会いのきっかけは、淡路島にある「樂久登窯」。窯元の西村さんは同級生で、最初は、料理がなくても器単体として格好いいものを作っていたんです。だけど僕は「料理を持った時に『良い器ですね』と言われるものがほしい」と15年前から伝え、少しずつ料理が映える器を作ってくれるようになりました。この器にこの料理を盛ると、1.3倍美味しそうに見えて、より美しく、食べやすく、温度を変えずに盛り付けられる。そんな相乗効果が得られるものが、良い器なのではと考えるようになりました。
「十皿」をオープンして5年ほどの間に、生産者さんや農家さんだけでなく窯元も巡るようになりました。
器を買うポイントは「この器にこの料理を盛りたい」というのが2~3品思い浮かんだら、買うことにしています。どんなに格好よくても思いつかない時もあります。あと、僕の料理との相性も考えるようになりましたね。逆に、器は同じ作り手さんが同じ窯で焼いても一緒のものは絶対出来上がらないし、一期一会のものなので、いいなと思ったら在庫があるだけ買います。
最近は、淡路島の大前悟さんという器作家さんのものが大好きなんです。良い土をスコップで地層ごと持ってきてそのまま焼いていて、中に大きな石がゴロっと入っていたり、色の違いがあったりします。そういう器に、シンプルに焼いたトマトや玉ねぎを載せるとすごく相性がよくて。シンプルの極みのようなスタイルですが、色々な器を見ている中で、心が動かされるのはそういうものになってきています。
自然をより身近に感じる、新たなストーリーへの挑戦
―先ほどもお話にありましたが、シェフは淡路島で「島の十皿」というイベントを1年に1回行われていますね。
淡路島で生まれ育った私が、今できる一番の料理を、農家さん、漁師さん、陶芸家さんと一緒に、十の食材、十の器で表現しています。自分の中で、どこか淡路島と繋がっていたいという気持ちがあって。コロナ禍で2年お休みしていましたが、毎年9月頃に行っています。現地の人からも、お客様からも喜んでいただき「また行きたい」と言ってくださいます。
毎年場所を変え、新しいゲストを呼んでコラボし、できたらこれからも進めていきたいなと。2023年は「ヒラマツグミ」という設計事務所のカフェと敷地を借りて、次の新店で使う薪オーブンを持って行ってみようと。薪火で有名な芦屋にある「アンファロ」さんにもお越しいただいて、一緒に料理をしていただきました。
―今年、新店をオープンされるそうですが、次のお店は薪を使うお店なんですね!どのようなお店にする予定ですか?
11月にオープンする新店を一言で言うと「炎を見ながら、美味しくワクワクする料理を食べる店」。クローズキッチンではなく、カウンターキッチンで直接薪の炎を見ながら、五感で楽しむライブ感というか。僕のイメージとしては暖炉を囲むように、食事を楽しみながら薪料理を味わえるお店にしたいですね。今の「十皿」の進化バージョンのようなイメージで「十皿」の色々な料理を楽しみながら、要所要所で薪料理の魅力を出していきたいです。
本当は新しいお店も自分でやりたいんですが、それより自分のスタッフを支援していきたいなと。新店は5年間「十皿」のセコンドを務めてきた眞邉シェフに任せる予定です。
飲食店を営む上で大事なことの一つは、一緒に働く仲間。「一緒に店をやりましょう」と言ってくれるスタッフも「一緒にやろう」と言えるスタッフもあまりいなかったから、早く独立しなかったということもあるので。眞邉シェフはずっと支えてくれたんで、彼がやりたいことを精一杯応援してあげたいなと思っています。お客様も「彼がやるなら行くよ」と言ってくれて、11月の予約はもう埋まっているほど。「十皿」の最大のライバルは、新店かもしれません。そういう意味でのプレッシャーも感じて、切磋琢磨していけるから頑張れますね。
ある一定の年齢になってきたので、若いシェフを応援する気持ちが芽生えてきました。Instagramでも告知していますが「十皿」では『U-30シェフ応援プラン』という形で若いシェフに少し割引しているんです。
「ちゃんと勉強しに来ました」と言って食べに来てくれたら、絶対に元を取れるくらい、色々なことを伝えたいし吸収してほしいと思います。僕も新しいエネルギーを吸収したいし、逆にパワーをもらっているところもありますね。僕も若い時に、時間もお金もなくて本ばかり読んで勉強してたんですけど、やっぱり美味しい料理を食べて舌や目で覚えたことは一生忘れないという経験をしたので、今の若いシェフたちには自分ができることで応援していきたいですね。
【プロフィール】
真野 淳
1978年、兵庫・南あわじ生まれ。身近に畑のある環境で育ち、小学生のころから料理に親しむ。「ホテルオオサカサンパレス」で4年間フレンチの修行後、大阪・天満のイタリアン「スフィーダ」で料理長として約13年、北新地「香り串揚げ 口勝」で約2年勤務。2018年11月、20年以上に渡る料理人人生を凝縮した「十皿」を大阪・西天満にオープン。
【編集後記】
真野シェフの語る言葉からは、料理に対する姿勢や想いの強さを感じました。奇をてらった料理ではなく、純粋に美味しい料理を出して喜んでもらいたい。多くを語らずとも、美味しい理由を根底に論理付け、感情に訴えかける。「十皿」も「島の十皿」も、新しいお店も、それぞれの良い個性が循環していく、そんな印象を強く持ちました。
※こちらの記事は2024年10月28日更新時点での情報になります。最新の情報は一休ガイドページをご確認ください。